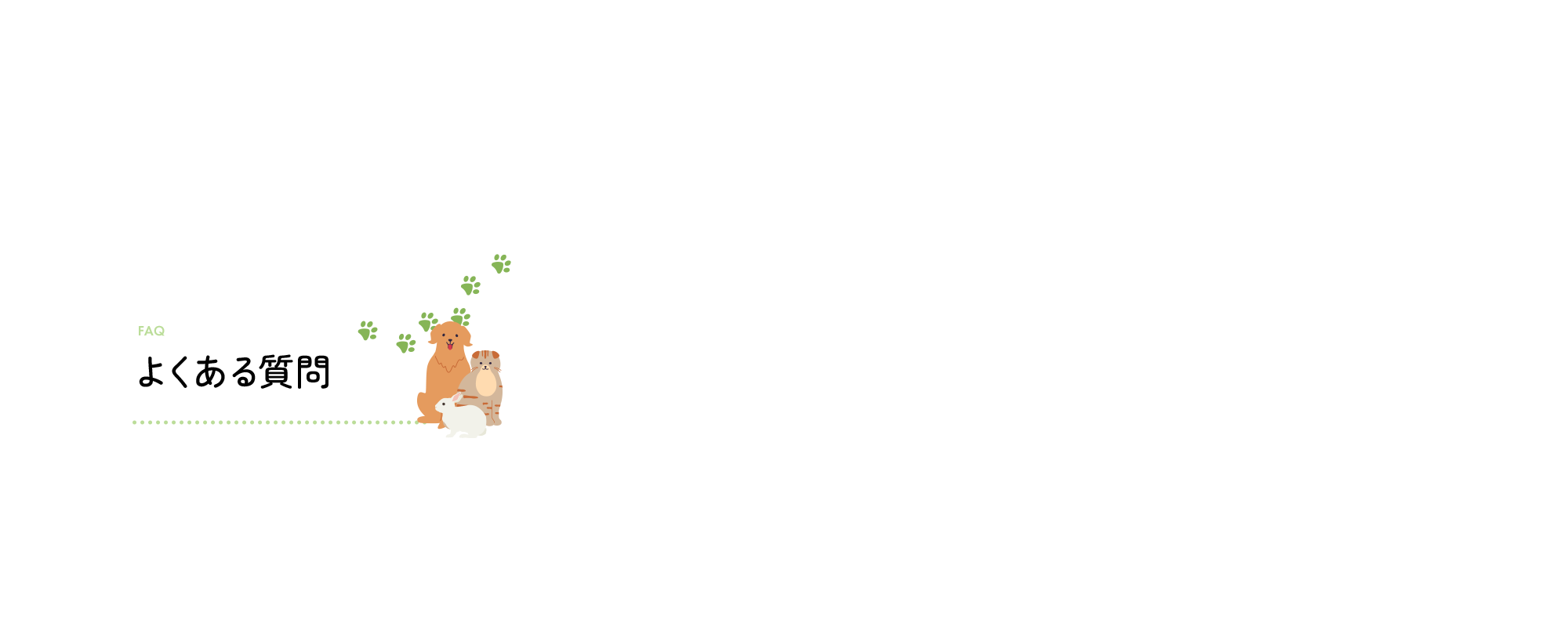診療やご来院に関するご質問
動物と暮らす毎日の中で、「これで大丈夫かな」「病院に行くべきか迷う」と感じる場面は少なくありません。よくある質問のページでは、診療のこと、トリミングのこと、来院時の注意点など、みなさまから寄せられる相談をまとめています。気になることがあるときの目安として、まずはこちらをご覧ください。それでも不安が残る場合は、いつでもお気軽にお問い合わせください。
一般的なご質問
一般的なご質問一覧
初診のときは、何か持っていくものが必要ですか。
特に必要なものはありませんが、他院で処方されたお薬(の名称がわかる書類でも可)や、獣医による診断書などがございましたら、診療の際に参考にさせていただきます。また、ペットの緊張を緩和するために、使い慣れたケージや、普段のおやつなどをお持ちいただくといいかもしれません。
フィラリア症と予防についてのご質問
フィラリア症と予防についてのご質問一覧
室内で飼っている場合は予防しなくてもいいですか。
確かに、屋外で飼われている犬と比較すれば、感染率は低いと思われます。しかしながら、まったく感染しないとは決していえないため、室内犬もぜひ予防しておくことをお勧めします。
蚊取り線香をしっかり焚いておけば大丈夫ですか。
いえ、フィラリアの予防は、決められた方法で薬を投与することにより、内科的に対処しなければなりません。人間も、いくら蚊取り線香を焚いていても蚊にさされるのと同様に、やはり犬も蚊にさされます。
なお、フィラリアの予防薬は虫除けの薬ではないため、飲んでいても蚊にさされることはあります。
犬の便から虫が出てきました。フィラリアに感染しているのでしょうか。
いえ、通常の場合、フィラリアは腸や便に出てくることはありません。おそらく腸内の寄生虫(回虫・鞭虫・鉤虫など)が出てきたものと考えられます。なお、寄生虫を駆除する効果を持つフィラリア症予防薬もあるため、投与後に寄生虫が便に混じる場合があります。
何月まで薬を飲ませればいいのでしょうか。
地域や気候によって、投与をやめる時期は異なります。また、同じ地域でも、年によって多少時期が変わる場合もあります。兵庫県南部では、だいたい11月あたりが目安となります。
予防接種(ワクチン)についてのご質問
予防接種(ワクチン)についてのご質問一覧
犬のワクチンはいつ受ければいいのですか。
狂犬病ワクチンは、生後90日以上の犬の飼育者に摂取が義務づけられているため、毎年1回必ず受ける必要があります。その他のワクチンは、通常の場合、生後2ヶ月と3ヶ月の時期に2回受けて、その後は年1回ずつ追加接種を受けるようにしてください。いずれの場合も、良好な健康状態のときに受けましょう。
いま妊娠していますが、ワクチンを受けても大丈夫ですか。
いえ、この時期は避けるべきだといえます。ワクチンは、毒性がない(または弱められた)病原体から作られ、弱い病原体を注入することで体内に抗体を作り、以後感染症にかかりにくくするためのものです。弱いとはいえ病原体を接種するため、仔への悪影響を考慮して、妊娠期及び授乳期は接種を控えましょう。
混合ワクチンを受けた後、どれくらいの時期から狂犬病ワクチンを受けられますか。
混合ワクチン等を受けた後、そのワクチンが生ワクチン(一般に、ウィルスが生きているワクチン)であったら1ヶ月以上、不活化ワクチン(一般に、ウィルスが死んでいるワクチン)であったら1週間以上の間隔をあければ狂犬病ワクチンを受けられます。
ワクチンを接種すれば、100%予防できますか。
その子が持つ免疫力によって、症状がでるかどうかが決まるため、残念ながら、100%予防できるわけではありません。ワクチンとは病原体が体内に侵入するのを防ぐのではなく、あくまでも症状が出るのを抑えるものとお考えください。
ワクチンを接種した後、何か注意することはありますか。
注射当日は安静にし、2~3日間シャンプーや激しい運動は控えましょう(注射後2週間は免疫が十分できていないため、戸外への散歩や他の犬との接触は避けてください)。また、神経質な犬や猫で、注射当日に痛みを訴えたり元気がなくなる場合は、安静にして、獣医師にご連絡ください。
なお、アレルギー体質の犬や猫では、まれに嘔吐、下痢、唇やまぶたのむくみ・かゆみがみられたり、痙攣や虚脱を起こすことがあります。そのような場合は、すぐに獣医師にご連絡ください。
避妊・去勢手術についてのご質問
避妊・去勢手術についてのご質問一覧
何才ごろに手術をするべきですか。
男の子・女の子ともに、生後6ヶ月程度から行っております。なお、メスの場合、初回発情前に手術を行うと、乳腺腫瘍の発症を高い確率で予防できることがわかっています(2歳を過ぎてからの手術では、これらの病気の予防にはなりません)。
不妊・去勢手術を受けることによって、性格が変わりませんか。
いえ、本来持っている性格が変わることはありません。そもそも性格は、犬で1~2才齢、猫で1才齢まで発達過程にあります。早期に手術を受けて、その後に性格が変わっとしても、その変化は手術を受けなかったたとしても生じるものと考えられます。
ご家庭での生活についてのご質問
ご家庭での生活についてのご質問一覧
飼っている犬や猫が迷子になりました。どうしたらいいのでしょうか。
まずは保健所にご連絡ください。また、近くの交番や動物病院にも連絡を入れてみてください。保護している場合や保護した方からの連絡があることもあります。張り紙やタウン紙などへの広告も効果的ですが、とにかく早めの対応が大切です。なお、東播獣医師会のホームページにも迷子情報が掲載されています。
初めて犬を飼うことになりました。日常生活でまず気をつけることは何ですか。
犬に限らず基本的な生活環境を整えてあげることがまず第一です。ただ、最近犬や猫の肥満(それによる糖尿病)が増えています。甘やかされて多くのおやつをもらったり、家族の食事中に人の食べ物をもらったりすることで、必要以上のカロリー摂取が大きな原因です。かわいくてついあげてしまう気持ちはわかりますが、結局人が犬や猫の肥満の原因を作っているのです。食事の量と運動の量のバランスに十分注意しましょう。
犬や猫のノミを駆除するにはどうすればいいのですか。
成虫(ダニにも有効)の駆除には、取扱いが簡単で効果的な滴下型(フロントラインスポット)がお勧めです。また、卵・幼虫・さなぎの駆除には、内服薬(プログラム)がお勧めです(ただし、イヌは年間を通して1ヶ月に1回内服。ネコは6ヶ月に1回の注射)。なお、最近ホームセンターなどでノミの外用薬が販売されていますが、効果の面ではあまり期待できないため、ノミでお悩みの場合は獣医師にご相談ください。
求人のご応募・お問い合わせについて
採用に関するご相談やご応募は、お電話にて受け付けています。働くうえで不安に感じていることや、仕事内容についての質問などがあれば、お気軽にご連絡ください。院内の雰囲気や業務内容を丁寧にお伝えし、安心して選んでいただけるよう対応いたします。